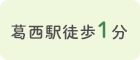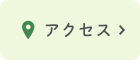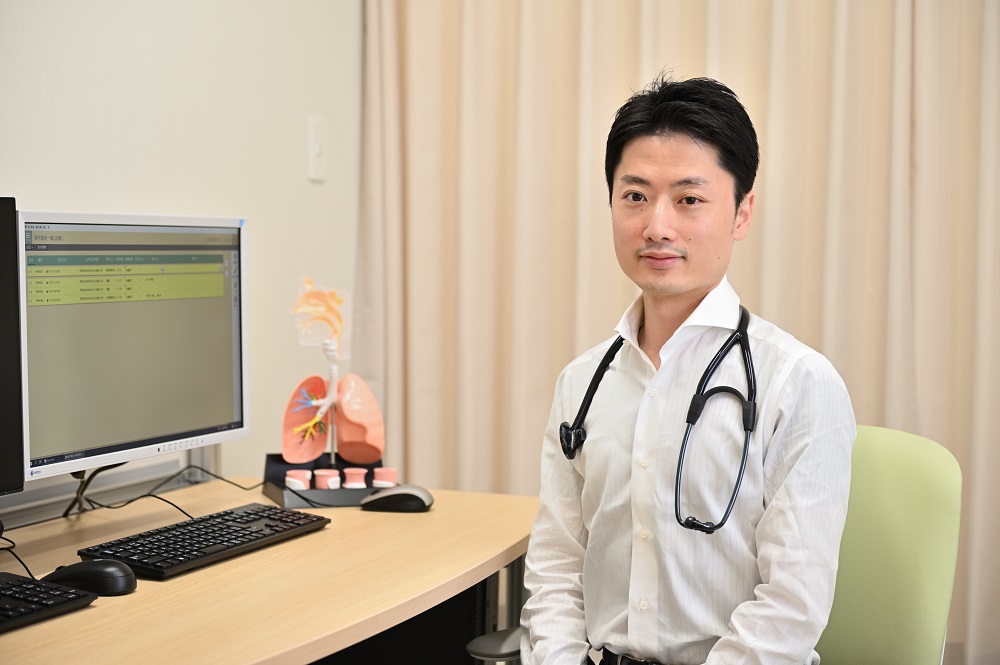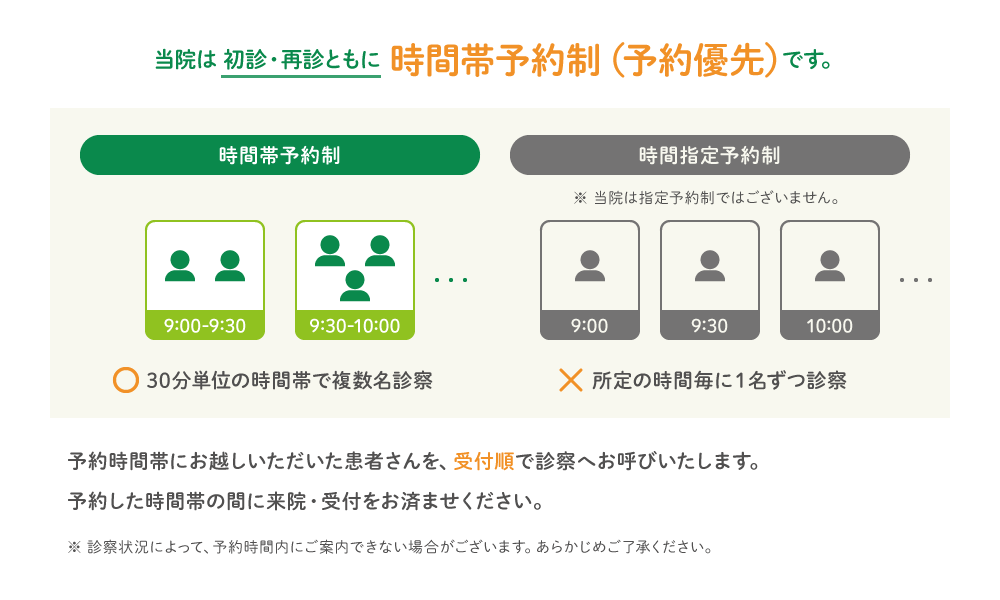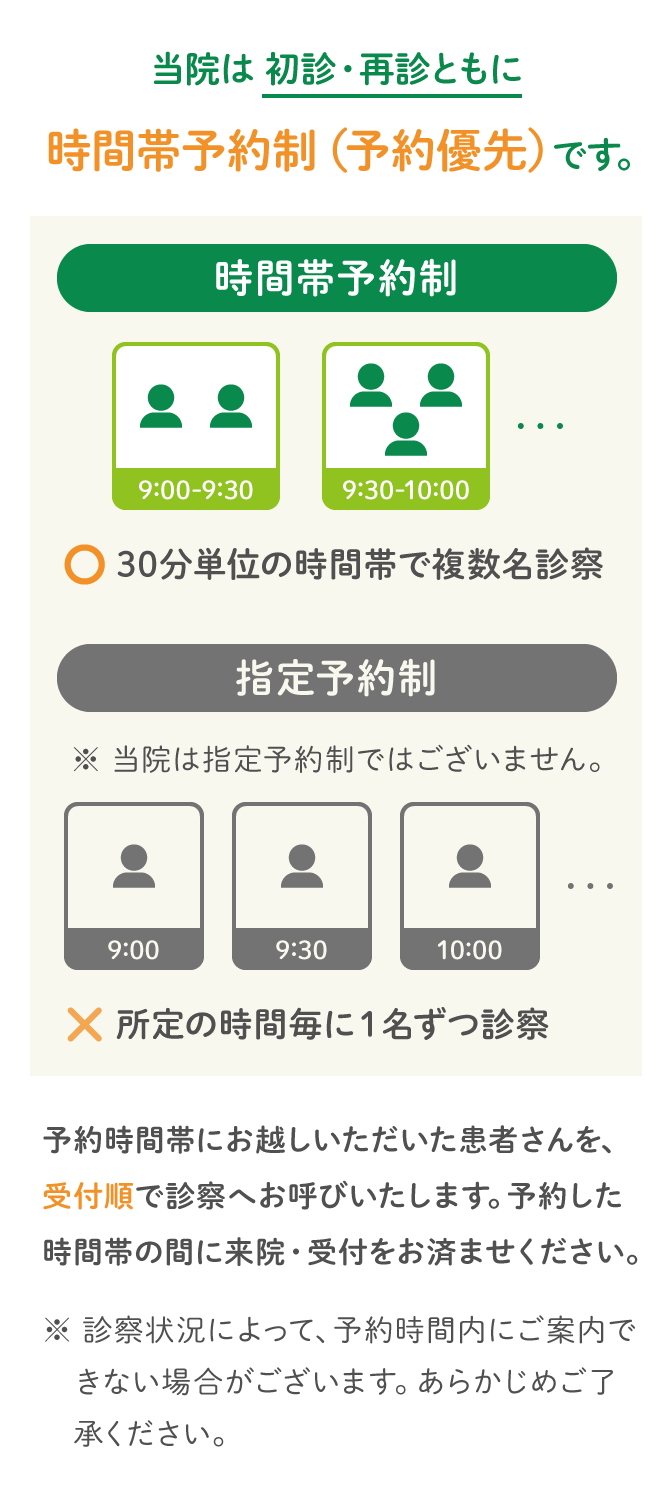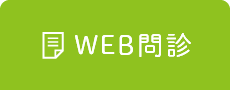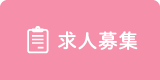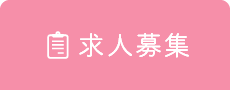2025年4月10日に行われました予防接種に関する講演会「ワクチン接種における患者さんの意思決定支援」と題して、演者として参加致しました。講演趣旨を下記にまとめておりますので、ご興味がある方はごらんください。
ワクチン接種における患者さんの『意思決定支援』
はじめに
2025年4月より、主に65歳の方を対象に帯状疱疹ワクチンの予防接種が予防接種法に基づく定期接種(B類疾病)として開始された。ところが既に定期接種(B類疾病)の対象となっている他のワクチンについても、現状では接種率が十分に高いとは言えない。例えば、高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチン、新型コロナワクチンはいずれも65歳以上の約半数が未接種という状況である。ワクチン接種率を向上させるためには、医療従事者から患者さんへの積極的な接種勧奨が不可欠と考えられている。では、患者さんに対し帯状疱疹ワクチンについて「何を」「どう」伝えるべきだろうか。本講演では、「患者さんの意思決定支援」という視点からこの問いについて考えていく。
Agenda
・Vaccine Preventable Disease(VPD)とB類疾病ワクチンの現状
ワクチンで予防可能な疾病と、定期接種B類に指定されている成人対象ワクチンの接種状況
・ワクチンの接種率向上のために、患者さんに「何を」伝えるべきか?
患者さんに提供すべき情報の内容
・ワクチンの接種率向上のために、患者さんに「どう」伝えるべきか?
患者さんへの伝え方・関わり方
・当院での多職種SDMによる帯状疱疹ワクチン勧奨の実際
演者のクリニックでの多職種協働による帯状疱疹ワクチン接種勧奨の取り組み例
定期接種の分類と帯状疱疹ワクチン
日本の予防接種法における定期接種にはA類疾病とB類疾病がある。B類疾病とは個人の発病・重症化予防に重きを置いたもので、接種による集団予防効果も期待されるが、A類疾病と異なり「個人の接種努力義務がなく、市町村長による接種勧奨も行われない」分類である。帯状疱疹はこのB類疾病に該当する。すなわち、帯状疱疹ワクチンを接種するかどうかは患者さん自身の意思決定に委ねられており、医療従事者にはその意思決定を支援する役割が求められる。現場では、主治医がワクチンの提案や情報提供をしなければ患者さんが医療機関でその情報を得る機会を失ってしまう。したがってワクチン接種率向上には、主治医による積極的な接種勧奨が欠かせないと考えられる。しかし実際には、「患者に押し付けがましいと思われないか」「勧めても断られるのではないか」「関係性が悪化しないか」「説明に時間がかかる」「そもそも説明するきっかけがない」といった理由で、勧奨したい気持ちはあってもどう患者さんと向き合えばよいか迷う声も多く聞かれる。
成人対象B類疾病ワクチンの現状(肺炎球菌ワクチン)
定期接種B類疾病として65歳以上に公費助成が行われている肺炎球菌ワクチン(PPSV23)の接種率は、年齢層が上がるにつれてやや向上する傾向があるものの、65歳以上の約半数は接種を受けていないのが現状である。さらにPPSV23は5年後に再接種が必要だが、再接種率は初回よりもさらに低いと予想される。高齢者肺炎の罹患や重症化を防ぐため、まだ多くの未接種者がいることが課題である。
成人対象B類疾病ワクチンの現状(インフルエンザワクチン)
高齢者の季節性インフルエンザワクチンについても接種率は十分とは言えない。65歳以上の接種率は50%未満であり、2人に1人ほどが接種していない計算になる。インフルエンザは毎年流行する身近な感染症であるにもかかわらず、高齢者においても未接種者が多い状況である。
成人対象B類疾病ワクチンの現状(新型コロナワクチン)
新型コロナウイルスワクチンもまた、高齢者の接種率が決して高いとは言えない。政府発表によれば、令和5年(2023年)秋開始の高齢者向け追加接種分での接種率は約50%程度にとどまった。さらに、令和6年(2024年)秋開始分では自己負担の発生も予定されており、接種率は一層低下すると予想されている。
成人対象B類疾病ワクチンの現状(まとめ)
以上のように、成人(高齢者)を対象としたB類定期接種ワクチン(肺炎球菌、インフルエンザ、新型コロナ)では、いずれも未接種者が約半数存在する状況である。特に自己負担が生じる場合や再接種が必要な場合、接種率が伸び悩んでいる。現状の接種率の低さには、高齢者本人のワクチンに対する意識や費用負担、周囲からの働きかけの不足など様々な要因があると考えられる。
日本人のワクチン接種意向(アジア5地域比較調査)
製薬企業モデルナ社が実施したアジア5地域(日本、台湾、香港、シンガポール、韓国)のワクチン意識調査によれば、日本は新型コロナワクチンの接種意向が5地域中最も低い結果であった。具体的には、「接種する」と回答した日本人は28.5%にとどまり、「接種しない」とした人が41.3%と過半数を超えた。5地域平均の「接種する」意向45.3%と比べても、日本の低さが目立つ。さらに、新型コロナとインフルエンザの同時接種の意向についても日本が最も低く、「同時に接種する」と答えたのはわずか13.3%であった(5地域平均32.9%、最高は香港46.5%)。過去12か月間に60歳以上の高齢者においてコロナワクチンもインフルエンザワクチンも「いずれも接種していない」人が44.9%にのぼることも報告されている。接種に消極的な理由としては、「副反応が心配」「新しい変異株にワクチンは効果がない」といった回答が多く、「接種費用が負担」という理由を上回ったという。また、「新型コロナやインフルエンザ、RSウイルス、肺炎球菌それぞれのワクチン接種は重要ではない」と答えた人の割合も日本が37.3%と突出して高く、他国を18ポイント以上上回った。さらに「ワクチン効果についての情報が得られた時」「安全性が保障された時」「流行の報道を見た時」といったいずれの条件でも「接種の動機にならない」と答えた人の割合が日本で最も多かった。この調査結果から、日本では副反応等への不安が強く、ワクチン接種の必要性自体を感じていない層が多いことが明らかになっている。以上の背景から、高齢者へのワクチン接種率向上のためには、接種によるメリットや安全性についての十分な情報提供と不安の払拭が一層重要であると考えられる。【4】
ワクチン接種意向と行動の関連因子(肺炎球菌ワクチンの例)
ワクチン接種率向上のためにはどのような要因が有効なのだろうか。2018年の樋口らの研究では、65歳以上の肺炎球菌ワクチン接種に関するアンケート調査を解析し、以下の3つが接種行動に関連する重要な要素であると報告された(※肺炎球菌ワクチン未接種群の分析)【5】。
・患者さん自身がワクチンの存在を認知していること(ワクチンがあると知っているか)
・患者さんがワクチンの有効性を認識していること(ワクチンで効果があると理解しているか)
・医療従事者からワクチン接種を勧奨されること(かかりつけ医などから勧められたか)
上記の要因が満たされるほど、接種率が高くなる傾向が示されたのである。一方、ワクチン接種をためらう理由として多かったのは「興味がない」「必要性を感じない」「副作用が心配」等であった。この結果を踏まえ、医療従事者は単にワクチンの有効性を説明するだけでなく、「接種しなかった場合に患者さんが背負うかもしれない疾病負担」や「接種した場合に起こりうる主な副反応」についても含め、丁寧な説明を行う必要がある。つまり患者さんにとって、疾病そのもののリスクとワクチン接種のメリット・デメリットを理解することが接種の意思決定に大きく関与するということである。
ワクチン接種率向上のために患者さんに「何を」伝えるべきか
以上を踏まえると、患者さんのワクチン接種の意思を後押しするには何を伝えるか(情報内容)が極めて重要である。患者さんに提供すべき情報のポイントは以下の4点に整理できる。
・対象疾患とその疾病負担について – ワクチンで予防できる病気はどのようなものか、その病気にかかった場合どんな症状・合併症や負担があるのか
・疾病予防のためのワクチンが存在すること – その病気を防ぐ手段としてワクチン接種という選択肢があること
・ワクチンの有効性 – ワクチンを接種するとどれだけ発症や重症化を減らせるのか、効果の程度や持続期間
・ワクチンの安全性(副反応) – 接種に伴って起こり得る副反応(副作用)にはどのようなものがあり、その頻度や程度はどのくらいか
患者さんには上記の情報をバランスよく伝える必要がある。これらによって、患者さんは「病気にかかるリスク」と「ワクチンで得られるメリット・デメリット」を理解しやすくなり、適切な判断につながる。
ワクチン接種率向上のために患者さんに「どう」伝えるべきか
次に、どう伝えるか(伝え方・関わり方)の工夫も重要である。帯状疱疹ワクチンを含むB類定期接種では先述の通り、接種するか否か最終的には患者さん本人の意思に委ねられる。だからといって患者任せにするのではなく、医療従事者が患者さんの意思決定を支援する姿勢が求められる。医師がワクチンという選択肢を患者さんに提案するかどうかは医師の裁量に委ねられているが、仮に提案しなければ患者さんはその情報を知る機会を逃してしまう。そのため、主治医によるワクチンの積極的な提案・勧奨が接種率向上には欠かせない。しかし前述のような様々な懸念(押し付けに感じられないか、断られるのでは等)から、ワクチン勧奨は医療現場で容易ではない側面がある。なぜワクチン接種の勧奨は難しいのか?――その本質には、「ワクチン接種の勧奨」という行為を通じて医師が患者の意思決定支援に関わることの難しさがあると考えられる。本講演では、ワクチン接種における患者さんの「意思決定支援」の在り方についてさらに深く考えてみたい。
「ワクチン接種における患者の意思決定支援」とは
ここからは「意思決定支援」という概念について整理する。医療における意思決定プロセスには、大きく3つのアプローチのモデルが知られている。
1.パターナリスティック・モデル(従来型)
医師がエビデンスに基づき最善と思われる治療方針を決定し、患者に説明して同意を得るアプローチ。患者さんは医師の決定した治療方針に基本的には従う形になる。これは伝統的なインフォームド・コンセントの形態ともいえる。
2.インフォームド・チョイス・モデル
医師は考え得る選択肢とその根拠・情報を提示するが、どの治療を選ぶかは患者の価値観に委ねるアプローチ。患者さんは提供された情報をもとに自ら治療選択を行う。
3.シェアード・デシジョン・メイキング(Shared Decision Making; SDM)モデル
医師と患者が協働して意思決定するアプローチ。医師はエビデンスに基づき現実的に受け入れ可能な複数の治療選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを説明する。また医師自身の推奨も伝えつつ、患者さんの価値観や考えを踏まえて共に治療方針を検討し合意形成する。患者さんは選択肢の内容を理解し、医師と対話しながら最終的な治療方針に合意する。
以上の3つのモデルはCharlesらによって提唱されたものであり、現在では特にSDM(共有意思決定)が患者中心の医療を実現するアプローチとして注目されている。SDMの構成要素としては、「少なくとも医療者と患者が関与すること」「両者が情報を共有すること」「双方が希望する治療について合意を形成する段階を踏むこと」「実施する治療について合意を得ること」が挙げられている。【6】
SDM(共有意思決定)の効果
SDMを実践すると、医療の様々な面でプラスの効果が得られることが研究で示されている。例えば、SDMの導入によって患者満足度が向上し、さらに治療アドヒアランス(治療遵守度)が改善するとの報告がある。また、患者の不安や心配といった心理的側面の症状が軽減されることも指摘されている。一方、SDMは医療者側にも変化をもたらす。SDMを取り入れることで、医師が患者さんの社会的背景により関心を払い、生活への影響や治療に対する疑問についてよく耳を傾けるようになるという報告がある。【7】【8】【9】【10】加えて、SDMの効果を定量的に示した研究として、SDMを用いた介入が高齢者肺炎球菌ワクチンの接種率に与える影響を調べたメタアナリシスがある。それによれば、SDMによる介入を行った群は、非介入群に比べ肺炎球菌ワクチン接種率がおよそ2.26倍に向上した(OR=2.26, 95%信頼区間1.60–3.18)という。【11】また同研究では、SDMプロセスの3つの側面(「患者の活性化」「双方向の情報交換」「双方向の選択肢検討」)についてサブグループ解析を行い、興味深い知見が報告されている。すなわち、患者の活性化(患者に積極的に考えてもらう支援)は医師よりもパンフレット等テキストの配布や看護師による支援の方が効果的であり、情報の双方向交換(患者との対話による情報共有)は医師よりも看護師が担う方が効果が高いが、選択肢の双方向検討(治療法の相談・意思決定)は看護師よりも医師が担う方が効果が高いという。【11】この結果は、SDMの実践においては医師だけでなく看護師など多職種の関与が有用であり、役割分担によって効果的な意思決定支援ができる可能性を示唆している。
SDMに関する指針(NHSイングランドの定義)
イギリスNHS(国民保健サービス)でもSDMの普及が進められており、NHSイングランドによるSDMの定義が紹介された。それによれば、SDMとは「利用可能な治療選択肢のリスク・メリットと予想される結果を患者が理解し、エビデンスに基づく質の高い情報と個人の嗜好(好み)に基づいて望ましい治療方針を決定できるよう支援すること」である。緊急でない状況で医療やケアについて複数の選択肢(何もしないことを含む)がある場合に有効であり、SDMによって患者は自分の価値観に沿った意思決定ができるよう支援され、その結果エビデンスに沿った治療方針を実行する可能性と治療転帰(アウトカム)が改善し、決定を後悔するリスクが減少すると述べられている。また、SDMのプロセスを通じて患者のヘルスリテラシー(健康情報を理解し活用する力)に対応することで健康格差の是正にもつながり得ると指摘されている。【13】
さらに、Durandらの研究では、ヘルスリテラシーや社会経済的地位の低い患者に対してこそSDMは有用であることが示された。そのような患者にSDMを用いた介入を行うと、知識の向上、インフォームドチョイス(十分な情報に基づく選択)の増加、意思決定への参加度の向上、自己決定効力感の向上、SDMへの意欲の増加といった成果が得られたという。【12】ただしその際には、難解な医療用語を避け平易な言葉を用いること、情報提供のレイアウトや形式を簡潔にすることなど、特別な配慮が必要であるとも報告されている。【12】ヘルスリテラシーの低い患者さんほど医療者側からの意思決定支援が重要であり、SDMのアプローチはそうした患者さんに積極的に適用すべきであるということである。
当院での多職種SDMによる帯状疱疹ワクチン勧奨の実際(導入)
以上の知見を踏まえ、演者のクリニック(葛西よこやま内科・呼吸器内科クリニック)で実践している多職種(医師・看護師)によるSDMを用いた帯状疱疹ワクチン接種勧奨の取り組みが紹介された。まず、取り組み当初の状況では、患者さんに帯状疱疹ワクチンのパンフレット(説明資料)を配布するのみで特別な説明はしていなかったところ、10人に配布して実際に接種に至った患者さんは0人であった(黎明期:0/10人)と振り返られた。一方、その後SDMの考え方を取り入れ、パンフレット配布に加えて看護師が患者さん個別に声かけや説明を行う体制を導入した結果、400人にパンフレットを配布して40人が接種希望を表明した(多職種SDM介入後:40/400人)とのことである。これは接種希望率が0%から10%へと向上したことを意味する。これら400人はいずれも当時は公費助成がない自費診療で、ワクチン費用は1回あたり22,000円(帯状疱疹ワクチンは2回接種)という条件下であった。
さらに、自治体による助成が開始された後の状況として、東京都で助成制度(1回あたり自己負担12,000円に軽減)が導入された結果を含めると、2025年2月18日時点で当院では950人にパンフレットを渡し、そのうち304人が接種を希望したというデータが示された。これは**約32%**の接種希望率に相当し、費用負担の軽減も接種意思を後押しした可能性がある。当院での経験では、SDMによる丁寧な情報提供・意思決定支援を行うことで、費用や副反応への不安があっても接種を前向きに検討する患者さんが着実に増加した。
当院での多職種SDM勧奨モデル(ケーススタディ1)
ここで、実際の診療場面を想定したケーススタディが紹介された。ケース1は、50歳の女性患者(既往歴:気管支喘息)である。帯状疱疹ワクチンは50歳以上から接種可能であり、この患者さんも対象となる。診察の場面で、まず看護師が「私がお話を担当しますね」と声をかけ、患者さんへの説明を始める設定である。看護師はこの患者さんに対し、次のような情報提供を行った。
・「帯状疱疹の発症は近年増加しています。50歳以上では、ほぼ100%の人が水痘帯状疱疹ウイルスを体内に持っており、免疫力が低下すると誰でも発症する可能性があります。生涯で3人に1人は帯状疱疹を発症すると言われています。また、一度発症しても再発することがあります」
・「帯状疱疹は加齢とともに発症が増加し、50代から80代までの年齢層で全体の2/3を占めることが分かっています。50代の方も、すでに帯状疱疹が起こりやすい年齢に入っていると言えますね」
これらの説明を聞いた患者さんは、「確かに、1年あたりのリスクで考えるとそれほど高くない感じかもしれませんね」と、自身の印象を述べた。つまり、「一生のうち3分の1」と言われてもピンと来ないが、「一年間で見れば発症確率は数%程度ではないか」という感覚で、それほど切迫した危険とは感じない、という反応である。
そこで看護師は、患者さんの認識を踏まえつつ、ワクチンを接種する場合と接種しない場合の比較を提示した。具体的には、「帯状疱疹ワクチンを接種する選択肢」と「接種しない場合に考えられるリスク」を対比する図表を用い、以下の点を説明した。
・ワクチンを接種すれば、将来の帯状疱疹発症を約10年間予防できる可能性がある。一方で、費用は2回で約4万円かかり、副作用として一定期間痛みや腫れ、発熱等が生じるリスクがある。
・ワクチンを接種しない場合、将来帯状疱疹にかかるリスク(生涯発症率1/3)をそのまま背負うことになる。実際に発症してしまった場合には、その病気自体による苦痛や生活への支障(疾病負担)が生じるほか、治療にも費用がかかる(経済負担)可能性がある。
看護師は最後に患者さんに向けて、「『ワクチンの予防効果』と『ワクチン接種費用』を比較した上で、ご自身の価値観に基づき接種するかどうか決めましょう。結論はすぐに出さなくて大丈夫ですから、ゆっくり考えてくださいね」と優しく声をかけた。このように、情報を提供しつつ患者さん自身に判断を委ね、時間をかけて検討してもらうという姿勢がSDMのポイントである。
当院での多職種SDM勧奨モデル(ケーススタディ2)
ケース2では、60歳の男性患者(既往歴:脳梗塞、脂質異常症、高血圧、COPD〈慢性閉塞性肺疾患〉、喫煙歴20本×40年)を例に挙げている。ワクチン接種歴として、インフルエンザワクチンは毎年接種し、新型コロナワクチンも4回目まで接種済みという、予防接種に比較的前向きな患者さんである。この患者さんが定期受診で来院した場面を想定し、主治医(演者)が心の中で「(ワクチンを勧める良い機会かな・・・)」と考えるところから始まる。実際の診療でも、予防接種に前向きな患者さんに対しては、他のワクチン(この場合帯状疱疹ワクチン)を提案しやすいタイミングと言える。
医師は診察の中でこの患者さんに対し、次のように説明した。
「60歳代は帯状疱疹の好発年齢なのですが、『心血管疾患』や『COPD』などの基礎疾患をお持ちの方ではさらに帯状疱疹発症のリスクとなることが分かっています」
このように、患者さん本人のリスク因子(脳梗塞の既往=心血管疾患、COPDなど)が帯状疱疹の発症リスクを高めるエvidenceがあることを伝え、患者さん個人に即した理由付けでワクチン接種を提案する。実際、日本人高齢者を対象とした研究でも、心血管系疾患や肺疾患などの持病が帯状疱疹発症と関連するとの報告がある。【20】この患者さんは既に他のワクチンを積極的に受けている背景もあり、帯状疱疹ワクチンについても医師からの説明を受けて納得すれば、接種を前向きに検討すると考えられる。医師は患者さんの質問や懸念にも答えながら、SDMのプロセスに則って意思決定を支援していく。こうした個別具体的な働きかけにより、患者さん自身が「自分は帯状疱疹になるリスクが高いのでワクチンを受けておこう」と判断しやすくなることが期待される。
結語(まとめ)
本講演では、定期接種B類疾病を取り巻く現状と課題について概説し、帯状疱疹ワクチンの接種率向上に向けた考え方を述べた。B類疾病の定期接種とは「接種努力義務がなく、市町村からの積極的勧奨もない」ワクチンであり、接種するかしないかの決定は患者さん本人の意思に委ねられている。したがって、医療従事者にはワクチン接種の勧奨を通じて患者さんの意思決定を支援する役割が求められる。ワクチン接種率を上げるためには、まず患者さんがワクチンの存在を認知すること、そして医療従事者から患者さんへ「疾病の負担」「ワクチンの有効性」「安全性」といった情報提供が行われること、さらに医療従事者がそのワクチンを患者さんに推奨することが重要である。【5】本講演で紹介したShared Decision Making(SDM)は、医療従事者が患者さんの価値観に基づいて現実的な治療(予防策)オプションのメリット・デメリットを説明し、患者さんの意思決定を支援していくアプローチであり、ワクチン接種の場面においても有用であると考えられる。
Take Home Message
患者さんがワクチン接種をするかどうか自ら決められるようにするためには、医療従事者が患者さんに必要な情報を提供し、意思決定を支援することが重要である。ワクチンの恩恵が最大限に生かされるよう、医療者は一方的な押し付けではなく患者さんと対話しながら、納得のいく選択への手助けをしていくべきである。
参考文献(References)
1.日本臨床内科医会インフルエンザ研究班 編. インフルエンザ/COVID-19 診療マニュアル 2023–2024 シーズン版. 日本臨床内科医会; 2023.
2.国立感染症研究所. 感染症発生動向調査週報 (IASR) 2023年11月号;44(11):176-179, 2023.
3.厚生労働省. 新型コロナワクチンの接種回数について(令和6年4月1日公表); 2024.
4.モデルナ・ジャパン株式会社. 日本人のワクチン接種に関する意識調査結果(プレスリリース); 2024年11月13日.
5.Higuchi M, et al. Determinants of intention and action for pneumococcal vaccination in older adults: a community-based survey in Japan. BMC Fam Pract. 2018;19:153.
6.Charles C, Gafni A, Whelan T. Shared decision-making in the medical encounter: What does it mean? (Or it takes at least two to tango). Soc Sci Med. 1999;49(5):651-661.
7.Glass KE, et al. Medical informatics intervention: patient perceptions and patient satisfaction. Patient Educ Couns. 2012;88(1):100-105.
8.Shay LA, Lafata JE. Where is the evidence? A systematic review of shared decision making and patient outcomes. Med Decis Making. 2015;35(1):114-131.
9.Zolnierek KB, Dimatteo MR. Physician communication and patient adherence to treatment: a meta-analysis. Med Care. 2009;47(8):826-834.
10.久我咲子, 他. 総合診療におけるSDMの導入効果に関する研究. 日本プライマリ・ケア連合学会誌. 2016;39(4):209-213.
11.Kuehne F, et al. Shared decision making enhances pneumococcal vaccination rates in adult patients in outpatient care. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(23):9146.
12.Durand MA, et al. Do interventions designed to support shared decision-making reduce health inequalities? PLoS One. 2014;9(4):e94670.
13.NHS England, NHS Improvement. Shared Decision Making Summary Guide. NHS England; 2019.
14.Shiraki K, et al. Herpes zoster and its preventive vaccine in Japan. Open Forum Infect Dis. 2017;4(1):ofx007.
15.石川博康, 他. 帯状疱疹患者における帯状疱疹後神経痛の発症頻度. 日本皮膚科学会雑誌. 2003;113(8):1229-1239.
16.Merck & Co., Inc. ZOSTAVAX® (Zoster Vaccine Live) – Package Insert (USA); 2006.
17.Tseng HF, et al. Declining effectiveness of herpes zoster vaccine in adults aged ≥60 years. J Infect Dis. 2016;213(12):1872-1875.
18.Lal H, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015;372(22):2087-2096.
19.Cunningham AL, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016;375(11):1019-1032.
20.Takao Y, et al. Incidence of herpes zoster and risk factors for herpes zoster in Japan: a retrospective cohort study. J Epidemiol. 2015;25(10):617-625.
関連キーワード: #帯状疱疹 #予防接種 #定期接種 #ワクチン接種率 #意思決定支援 #SDM #多職種連携 #高齢者医療 #患者教育 #副反応