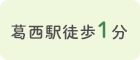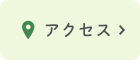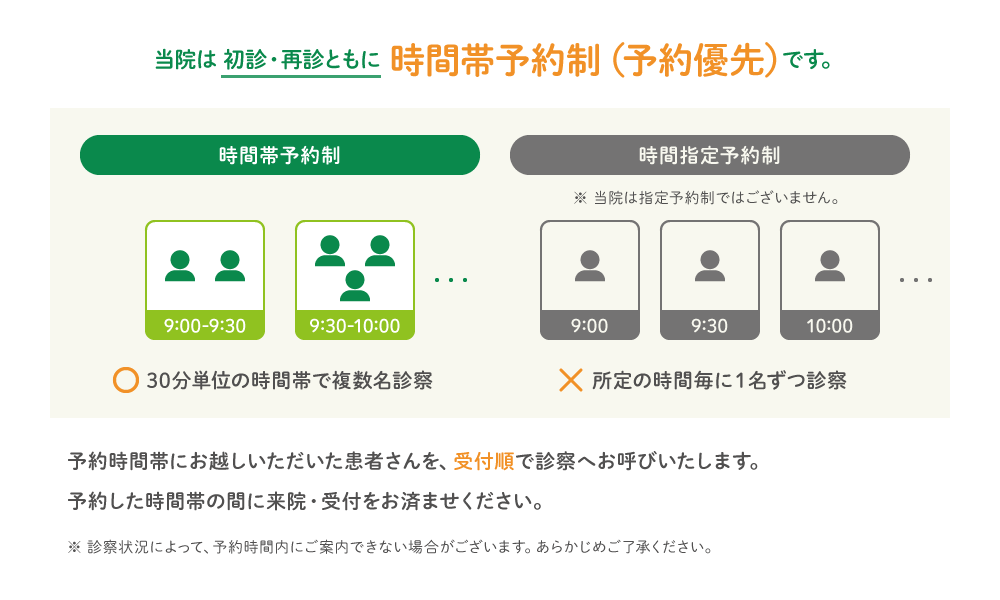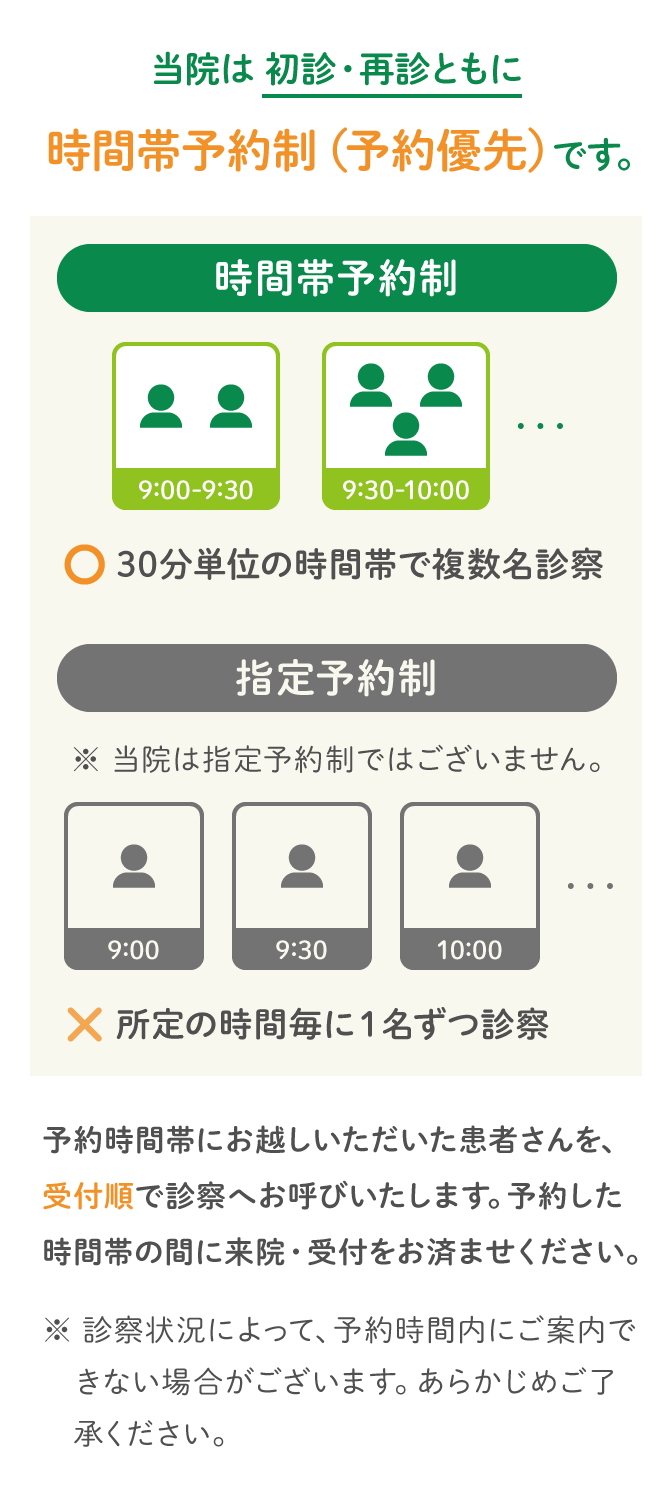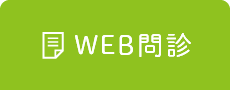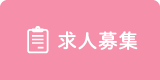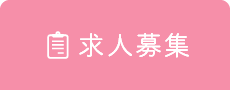2025年3月19日 webで行われました重症喘息の講演会に演者として参加致しました。重症喘息は最大限の既存治療を行ってもコントロール出来ず全身ステロイドを時に必要とする喘息をいいます。本講演では重症喘息患者さんに対し生物学的製剤をすすめる上でのポイントを中心にお話致しました。以下、講演録となりますのでご興味がある方はご覧ください。
重症喘息患者さんとのコミュニケーションで演者が大切にしていること
「患者さんに何を、どう伝えるべきか」を常に考える点が挙げられた。本講演ではそのポイントを、①重症喘息の診断と治療、②重症喘息の意思決定支援、③医療費負担、④ディシジョンエイドを用いた患者説明、という4つのテーマに沿って解説する。
重症喘息の診断と治療
重症喘息の疫学と負担
喘息は世界で約2億6200万人が患っている非常に一般的な疾患である(1)。日本でも人口の約8%(およそ1000万人)が喘息を有すると推定されている(2)。その中でも5~10%程度が従来の治療ではコントロールが難しい「重症喘息」に該当するとされる(3)。つまり国内だけでも数十万人規模の重症喘息患者さんが存在する計算であり、その疾病負担は無視できない。当クリニックでも現在100名以上の重症喘息患者さんが通院しており、全喘息患者さんのうち約5~10人に1人は重症喘息に当たる計算になる。
重症喘息の定義:
重症喘息(難治性喘息)は、可能な限りの最大限の治療を行ってもなお喘息の症状コントロールが不十分な状態を指す。具体的には、「高用量の吸入ステロイド(ICS)と長時間作用性β₂刺激薬(LABA)の併用に加え、必要に応じてロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)、テオフィリン、長時間作用性抗コリン薬(LAMA)、経口ステロイド(OCS)、生物学的製剤(後述)といった既存の治療を最大限使用しても喘息コントロールが不良な場合」や「これらの治療でコントロール良好であっても減量・中止すると症状が悪化してしまう場合」に重症喘息と定義される。なお、この定義を適用する前提として誤診でないか、吸入薬の手技やアドヒアランス(継続遵守)が確保されているか、増悪因子(アレルゲン、NSAIDs〈非ステロイド性抗炎症薬〉やβ遮断薬の使用、喫煙など)の除去や併存疾患(副鼻腔炎、肥満、アスピリン喘息〈AERD〉、COPDなど)の治療といった基本的事項への対応が十分になされている必要がある。このように適切な対策を講じてもなお既存治療でコントロール困難な喘息が「重症喘息」であり、国際的にもGINA(国際喘息ガイドライン)で定義される重症喘息とほぼ同義である要するに、「診断が正しい本物の喘息」に対して考えうる最善の治療を尽くしても症状が抑えられない状態が重症喘息ということになる。
重症喘息の問題点:
重症喘息では上述のように既存治療で十分なコントロールが得られないため、患者さんは普段から咳や痰、息切れなどの症状が続き、夜間に苦しくて眠れないこともあり、日常生活に支障を来しやすい。実際、コントロール不良な喘息患者さんでは健康関連QOL(生活の質)や仕事・社会活動への影響も大きいことが報告されている(10)。また、風邪などをきっかけに症状が急激に悪化(増悪)すると、予定外で医療機関を受診しなければならない。増悪時の治療には全身作用のステロイド(経口または点滴)が用いられるが、ステロイドは症状を速やかに改善させる一方で副作用への懸念が大きい治療である。特に経口ステロイド(プレドニゾロンなど)は、「たとえ少量・短期間の使用でも繰り返し累積することで将来的に全身の様々な副作用リスクとなる」ことが知られている(4)。具体的な副作用として、胃潰瘍(消化管障害)、骨粗鬆症や筋力低下(サルコペニア)、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患、糖尿病(代謝異常)、うつ病(精神面の副作用)、肺炎や敗血症など陥ってしまう。以上のように、重症喘息では症状面でも将来的な合併症リスクや臓器ダメージの面でも患者さんの負担が大変大きい。の重篤な感染症、皮膚のニキビ、白内障・緑内障等、身体のほぼ全ての臓器系統にわたり様々な有害事象が蓄積的に生じうる。また、そのリスクはステロイドの維持量が高いほど高まることが示されている(4)。一方で、こうした副作用リスクがあるためにステロイドの連用は避けたいものの、重症喘息ではステロイドを減らすとたちまち症状が悪化してしまうケースも多く、患者さんと医療者双方にとってジレンマとなっている。さらに、重症喘息患者さんでは増悪を繰り返すほど肺機能(1秒量)が著しく低下することも問題である。例えば日本人喘息患者を長期追跡した研究では、増悪が年に0回の患者さんの肺機能年下降量は約13.6 mLだったのに対し、年1回増悪する患者さんでは約41 mL/年、年2回以上増悪する場合は約58 mL/年もの肺活量低下が認められた(5)。このように頻回の増悪は気道の「老化」や不可逆的な構造変化(リモデリング)を招き、次第に治療に反応しにくい状態へと陥る。実際、肺機能が低下すると次の喘息増悪も起こりやすくなることから、負のサイクルにこうした背景から、「いかにステロイドの使用や増悪を減らし、喘息コントロールを改善するか」が重症喘息治療の重要課題となっている。従来の吸入薬のみでは限界がある重症喘息患者さんに対し、近年では「生物学的製剤」と総称される新たな治療オプションが登場しつつある。(スライド9) 生物学的製剤とは、喘息の気道炎症で重要な役割を果たす分子(サイトカインや抗体など)をピンポイントで標的として抑制する抗体医薬品のことである。言い換えれば、喘息増悪の原因となる特定の免疫反応だけを狙い撃ちし、それ以外の部分には作用しにくい「オーダーメイド標的療法」である。そのため全身の免疫反応ごと抑え込んでしまうステロイドに比べ副作用が少ないという特徴がある。
現在、喘息治療に使用可能な生物学的製剤
・抗IgE抗体:
IgEという抗体(アレルギー反応に関与)の働きを抑える薬剤。代表例は**オマリズマブ(商品名ゾレア)**で、2009年に日本で発売された。
・抗IL-5抗体 / 抗IL-5受容体抗体:
好酸球を増やすサイトカインであるIL-5やその受容体を標的とする薬剤。代表例は**メポリズマブ(ヌーカラ)**で、2016年発売。他にベンラリズマブ(ファセンラ、2018年発売)などがある。
・抗IL-4受容体抗体:
IL-4/IL-13経路を抑制する薬剤。代表例は**デュピルマブ(デュピクセント)**で、2019年発売。アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎を合併する喘息患者さんにも有効である。
・抗TSLP抗体:
気道上皮由来のアラーミンサイトカインであるTSLPを標的とする最新の薬剤。代表例は**テゼペルマブ(テゼスパイア)**で、日本では2022年に使用可能となった。
※当クリニックでは現在、上記オマリズマブ、メポリズマブ、デュピルマブ、テゼペルマブといった生物学的製剤を採用・提供している。
生物学的製剤の登場により、重症喘息の治療目標は「増悪を抑えるだけでなく、普段の症状・生活の質も改善する」方向へ広がっている。実際、これらの新規治療は臨床試験において年間の喘息増悪回数をおよそ半分程度にまで減らし、経口ステロイドの維持量を減量・中止できる割合を大きく向上させる効果が示されている(6)(7)。例えば、メポリズマブ(抗IL-5抗体)の第III相試験では年間増悪率がおよそ50%低減し、重症増悪のリスクも有意に減少した。また別の試験では、経口ステロイド常用中の患者において約半数でステロイドの大幅減量(あるいは中止)が可能になることが報告されている(7)。こうしたエビデンスを踏まえ、国際ガイドラインGINAや日本の喘息ガイドライン(JGL2024)でも、生物学的製剤は従来治療でコントロール困難な重症喘息に対する有力な選択肢として位置づけられている。現在までに複数の生物学的製剤が次々と登場し、喘息治療は新たな局面を迎えつつある。しかし一方で、生物学的製剤は非常に高価な治療でもあり、また注射製剤であるため定期的な通院・投与が必要になる。こうしたハードルから、有効性が示されているにもかかわらず生物学的製剤の導入に二の足を踏む患者さんも少なくない。そこで次章では、生物学的製剤を提案・導入する際に医療従事者が行うべき意思決定支援について考える。
重症喘息の意思決定支援
生物学的製剤による治療効果と安全性が確認され、今後ますます重症喘息治療への導入が期待される中で、「いつ・どの患者さんに生物学的製剤を勧めるべきか」そして「その際に何をどう説明するか」が現場の課題となっている。講演者は呼吸器内科の開業医(クリニック医)としての立場から、生物学的製剤を患者さんに勧める際のポイントを提示した。まず、他分野の例として関節リウマチ(RA)治療の進歩が紹介された。2000年代以降、関節リウマチでも喘息と同様に生物学的製剤(抗TNFα抗体など)が相次いで登場し、治療が飛躍的に進歩した経緯がある。東京女子医大の大規模コホート研究(IORRA研究)によれば、2000年当時は関節リウマチ患者の寛解率(病気が落ち着いている人の割合)はわずか数%程度で大半の患者が高疾患活動性の状態にあった。それが生物学的製剤の普及した2018年頃には寛解率が50%を超えるまでに改善し、疾患活動性が高いままの患者はごく一部に減少したという(6)。治療薬の面でも、生物学的製剤の導入によりメトトレキサートなどの既存薬だけではコントロール困難だった患者の多くが安定し、ステロイド薬の使用率も低下した。このRAの例は、生物学的製剤を積極的に取り入れることで患者さんの長期予後が大きく向上しうることを示している。喘息においても、生物学的製剤(抗IgE抗体は2009年、抗IL-5抗体は2016年、抗IL-5受容体抗体2018年、抗IL-4受容体抗体2019年に日本導入)が使えるようになった今、適切な患者さんにこれらを早期に導入することで将来的な喘息コントロールと予後を改善できる可能性が高い。言い換えれば、旧来の治療だけに固執してステロイド漬けで悪循環に陥るよりも、タイミングを見て新しい選択肢を提示することが患者さんの利益につながるのである。では、実際に重症喘息患者さんに生物学的製剤の導入を検討する際、どのように意思決定支援を行えばよいだろうか。ここで参考になるのが、2021年に発表された日本の大規模インターネット調査「KOFU study」の結果である。この調査では重症喘息患者さんの治療選択に関する意識や経緯が解析されている。その中で、生物学的製剤に「まだ至っていない」患者さん(医師から勧められたが導入に至らなかった群)と「治療中」の患者さん(実際に生物学的製剤を使用中の群)を比較したデータが興味深い。
生物学的製剤に至らなかった患者さんの傾向と理由
①医療費負担への懸念:
生物学的製剤は高額であるため、「治療費が高額である」ことが導入の大きな障壁となっていた。
②自身の病状認識の不足:
自分が「重症喘息」であるという認識が乏しく、現在の病状の深刻さを患者さん自身が十分理解できていなかった。
③現状の対症療法で満足:
「症状が出たときだけ経口ステロイドを飲めばよい」と考え、現状の対症療法的な管理で十分と感じていた。
一方で、生物学的製剤を導入した患者さんの群では、高額療養費制度など医療費負担軽減策に関する情報提供を受けていた割合が高かったことも報告されている。さらに興味深い点として、総合的な医療費負担の大きさ(年間の医療費総額)自体は、生物学的製剤未導入群のほうがかえって大きい傾向も示された(7)。これは、生物学的製剤を使わず放置した結果として重症増悪による入院や救急受診、ステロイドの副作用対策などで長期的には医療費がかさんでしまっている可能性を示唆している。このKOFU研究から得られる示唆は、患者さんが生物学的製剤に踏み出せない背景には「費用」「病気の認識」「現状治療への満足」といった情報・意識のギャップがあり、医療者側の適切な情報提供でそれらのギャップを埋めることが重要だという点である。では具体的に、重症喘息患者さんの意思決定を支援するために医療従事者は患者さんに「何を」伝えるべきか。KOFU studyの知見も踏まえた、重症喘息以下のポイントを提示した。
重症喘息患者さんの意思決定支援のために伝えるべきこと
-
① 患者さん自身が現在「重症喘息」であることを伝える。
ポイント: なぜその患者さんが重症喘息に該当するのか、その理由や現在の病状の位置づけ(例えば「あなたは最大限の治療をしてもなお増悪を繰り返している状態」など)を分かりやすく説明する。患者さん自身が自分の喘息の状態を正しく認識できるようにすることが第一歩である。
-
② 生物学的製剤による治療の効果を伝える。
生物学的製剤を導入すると期待できるメリットとして以下の点を説明する:
1)喘息症状が改善すること(日常的な咳や息切れが和らぐ可能性)、
2)喘息による日常生活への支障が軽減すること(夜間の睡眠や仕事・家事など日常生活の質が向上する可能性)、
3)喘息増悪(発作)を長期的に予防できること(急な悪化や入院のリスクを減らせる)、
4)生物学的製剤が効く理由(患者さんの喘息に特有の炎症パターンに対してこの薬剤がどう作用するのか、機序を概説する)。
-
③ 全身性ステロイド内服をこのまま続けた場合の将来的なリスクを伝える。
上述したような副作用の蓄積による健康リスクや、肺機能低下による将来的な悪影響について説明する。患者さんが現在はステロイドで「しのげている」つもりでも、長期的には取り返しのつかないダメージが蓄積する可能性を理解してもらう。
-
④ 治療にかかる医療費の詳細と、費用負担軽減策について伝える。
生物学的製剤は薬価が高額だが、日本には**「高額療養費制度」といった公的支援制度があることを説明する。高額療養費制度を利用すれば、所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定され、それを超えた分は後から払い戻されるため実質的な自己負担は大きく軽減できる**(例えば一般的な所得の方であれば月額上限は約9万円程度※)。また、難病指定や自治体の助成制度など該当すれば費用補助を受けられる場合もある。治療費そのものだけでなく、利用可能な費用軽減策についても具体的に情報提供することが大切である。患者さんが経済面の不安を解消できるようサポートする。
-
⑤ 生物学的製剤の導入は、できるだけ早い段階から検討・紹介する。
重症喘息が疑われ、少なくとも年に2回以上経口ステロイドでの救急的治療を要した時点で、生物学的製剤という選択肢を患者さんに提示し始めることが望ましい。あまりに長年放置すると前述のように肺機能低下などダメージが蓄積してしまうため、タイミングを逃さず早期から選択肢に加えることがポイントである。
-
⑥ 一度断られても根気強く提案を続ける。
生物学的製剤の提案に患者さんが難色を示す場合も多いが、提案は1回だけで諦めずに、診察のたびに繰り返し説明・提案することが重要である。「最初は断ったが、何度も話を聞くうちに治療を決断した」という患者さんも少なくない。実際、KOFU研究でも担当医からの生物学的製剤の勧奨を一度断った患者さんでも、時間をおいて再提案することで受け入れるケースが多いことが示唆されている。
-
⑦ 可能であれば看護師や医療ソーシャルワーカー(MSW)など多職種チームで介入する。
医師だけでなく、看護師や薬剤師、MSWなどがチームとなって患者さんを支援することで、患者教育や経済的相談など多面的なフォローが可能となる。また、多職種で同じ資料(後述のディシジョンエイド等)を共有し情報提供することで説明内容の質を担保できるメリットもある。
次に「どう伝えるか」、すなわち効果的な伝え方についてである。講演では、限られた診察時間であってもポイントを押さえることで効率よく意思決定支援ができると強調された。特に「ナッジ理論(Nudge理論)」の活用が紹介されている。ナッジ理論とは、経済的インセンティブや強制を伴わずに人々の行動変容を促す手法のことであり、厚生労働省も受診勧奨策などに応用している(11)。例えば駅の階段に消費カロリー表示をしてエスカレーターより階段利用を促したり、トイレの便器にハエのマークを描いて狙いを定めさせる(オランダ・スキポール空港の有名な例)といったユニークな手法が知られる。医療においても、患者さん自身が望ましい選択肢を選ぶよう後押しするコミュニケーションはこの「ナッジ」に通じるものがある。具体的には、パンフレット(リーフレット)などのツールを用いて患者さんが自宅で情報を整理・熟考できるようにすることも有効なナッジとなりうる。興味が乏しそうな患者さんにはパンフレットを手渡し、「後でゆっくり読んでみてください」と伝えるだけでも、患者さんが自分のペースで考えるきっかけを提供できる。診察室で一度に全てを理解・判断してもらおうとせず、情報を持ち帰ってもらう工夫も重要である。また、「どう伝えるか」のもう一つのポイントは患者さんに選択の主体を持ってもらうことである。医療者側が一方的に「この治療をやりなさい」と押し付けるのではなく、患者さん自身が選ぶのだという姿勢を持って対話することが大切である。例えば、「あなたの今後が心配だからぜひ生物学的製剤を受けるべきです」と断定するのではなく、「医療者として○○が懸念されるので、△の点で□□という治療を検討してはどうかと考えています」と自分の提案理由を伝えつつ、最後は患者さんの考えを問いかけるなどの手法が有効だろう。実際の会話では、「これまでお話しした点について、どうお考えですか?」といった開かれた質問を投げかけ、患者さんの受け止め方や価値観を確認することが推奨されている。このように患者さんとの双方向のコミュニケーションを図り、患者さん自身が治療を選択したという意識を持てるよう促すことが意思決定支援では重要である。
医療費負担と支援制度の説明
重症喘息の意思決定支援において、経済的な情報提供は避けて通れないテーマである。生物学的製剤は高価な治療であり、患者さんにとって費用面の不安は大きい。そのため医療者は、治療効果だけでなく費用負担とその軽減策について丁寧に説明する必要がある。日本には前述した高額療養費制度があり、月々の自己負担額には上限が設けられている(例: 一般的所得の方で約9万円/月、高齢者や低所得者ではさらに低額の上限が設定されています)。この制度により、生物学的製剤のような高額な薬剤を使用する場合でも、患者さんが実際に支払う額は大きく軽減される。たとえば年間数百万円の薬剤費がかかったとしても、高額療養費制度を利用すれば自己負担上限以上の分は払い戻されますので、患者さんの年間負担額は大幅に圧縮される。また、多くの民間医療保険には高額療養費に連動した給付金制度などもあり、実質的な手出しは思ったほど大きくならないケースも多い。さらに、重症喘息が難病認定されていれば公費負担の対象になる可能性もあるため、各患者さんの状況に応じて利用できる制度を調べ、情報提供することが望ましい。費用に関する説明では、「高額だ」というデメリット面だけでなく「負担を減らす方法がある」という安心材料も含めて伝えることで、患者さんが前向きに治療を検討しやすくなる(7)。加えて、医療費と絡めて伝えるべき視点として短期的な費用と長期的なリスクの対比が挙げられる。患者さんは目先の費用に目が向きがちだが、医療者は将来的なリスク(放置した場合に起こり得る病状悪化や合併症によるコスト)も含めて説明する必要がある。講演では、近くで見たときは高さが違って見える2本の木も遠くから見れば逆転する、というたとえ話(視点を変えれば価値判断も変わる喩え)も出された(スライド20)。すなわち、「今月の医療費」と「将来のリスク」の両方を天秤にかけて考える視点を患者さんと共有することが大切である。生物学的製剤による「将来得られる効果」と「追加で発生する金銭負担」を比較衡量し、患者さんご本人にとってどちらが価値があるかを一緒に考えていく姿勢が求められる。
ディシジョンエイドを用いた患者説明
以上のように、重症喘息患者さんに伝えるべき情報は多岐にわたる。そこで有用なのが「ディシジョンエイド(意思決定支援用ツール)」の活用である。講演では「ディシジョンエイド作成のすすめ」として、講演者自ら作成した当院オリジナルの重症喘息ディシジョンエイドが紹介された。ディシジョンエイドとは、患者さんと医療者が共同意思決定(Shared Decision Making; SDM)を行う際に用いる情報提供・整理のためのツールであり、一種のパンフレット資料である(11)。興味がない患者さんにはパンフレット配布が最も有効であると前述した通り、ディシジョンエイドを渡しておけば患者さんは診察室で聞いた説明を自宅で振り返り整理しやすくなる。また多職種で介入する際も、この資料を共有しておけば説明内容の統一や質のコントロールが可能になる。まさに患者さんに「何を」伝えるかを一冊にまとめ、なおかつ「どう伝えるか」の工夫も凝らしたツールと言える。当院作成の「重症喘息ディシジョンエイド~重症喘息を理解するために~」第一版では、以下のような項目が盛り込まれている:
-
①重症喘息の疫学:
日本人の約8%(約1000万人)が喘息に罹患し、そのうち5~10%が重症喘息に相当すること(1)(2)(3)。100人の喘息患者さんのうち5~10人が重症喘息であり、当院にも100名以上の重症喘息患者さんが通院しているというデータも示した
-
②重症喘息とは何か:
「既存治療(高用量ICS/LABA/LAMAの吸入、モンテルカストやテオフィリンの内服)を最大限に行っても喘息増悪を来し、時に経口ステロイドが必要となる喘息」を重症喘息と定義し、最大限の既存治療でもコントロールできずステロイドが必要になる状態を示した。また、喘息治療ステップの図(JGL2024のステップ表)を引用し、全喘息患者のうち5~10%が重症に該当し、15~20%程度は最大治療でコントロール可能だが残りがコントロール不良で重症喘息になる旨を解説した。
-
③重症喘息の問題点:
既存治療で十分コントロールできないために日常生活に支障が出ること(例:咳や痰、息切れで夜眠れない等)、増悪時には予定外受診が必要になること、増悪治療に使う経口ステロイドには副作用リスクがあること、少量・短期でもステロイドには蓄積毒性があり将来のリスクとなること、喘息増悪を繰り返すと肺機能低下=「気道の老化」につながること、肺機能低下により次の増悪が起こりやすくなる悪循環が生じること――これらを箇条書きで示した(4)(5)。具体的な副作用例(胃潰瘍、骨粗鬆症、心筋梗塞、糖尿病、うつ病、感染症、ニキビ、白内障など)や肺機能低下のデータ(増悪回数ごとの年間FEV₁低下量の比較)も図表で示し、重症喘息をこのまま放置することの怖さを視覚的に伝えている。
-
④重症喘息の治療選択肢:
「最大限の既存治療でも増悪する重症喘息に対して」と前置きし、次の治療選択肢(生物学的製剤や気管支熱形成術など)があることを提示。当院制作の資料では、ガイドライン等を参考に生物学的製剤の適応をまとめたフローチャートも掲載している(引用)。それぞれの生物学的製剤について、どのような患者さんに効果が期待できるか(好酸球が高い場合は抗IL-5製剤、FeNO高値や鼻茸合併では抗IL-4/13製剤、IgE高値なら抗IgE製剤、など)を脚注で説明している。この部分は専門的だが、医師が患者さんに説明する際のガイドとしても使えるよう工夫している。
-
⑤生物学的製剤とは何か:
生物学的製剤の作用機序を示す図解(炎症のカスケードと標的分子)とともに、「喘息増悪の原因となる分子だけを標的として抑える抗体製剤で、副作用が少ない特徴がある」と定義を掲載。加えて現在当院で扱っている具体的な製剤名と標的(抗IgE:オマリズマブ、抗IL-5:メポリズマブ、抗IL-4/13:デュピルマブ、抗TSLP:テゼペルマブ)も一覧にして示した。これによって「生物学的製剤=どんな薬か」を患者さんが理解できるようにしている。
-
⑥生物学的製剤の効果:
季節変動や天候・感冒による喘息状態の変化の図を示し、生物学的製剤使用で喘息の**「普段の調子」**自体が底上げされるイメージを伝えている(季節ごとの症状波形が改善する図)。実際に「生物学的製剤は増悪を予防するだけでなく普段の調子も改善させる」と明記し、治療による長期的メリットを強調している。また、コントロール不良な喘息では生活の質や仕事への影響が大きいことを国内調査結果(Nagaseらの研究)で示し(10)、症状が良くなることが生活面にもたらす恩恵についても言及している。
-
⑦伝えるべき情報のまとめ:
最後に、「患者自身が重症喘息であること(その理由)」「生物学的製剤の効果(症状改善・生活の質改善・増悪予防・作用機序)」「経口ステロイド内服の将来リスク」「医療費の詳細」という患者さんに伝えるべき情報項目をリスト化している。これは前述した「何を伝えるか」のポイント①~④に対応する内容で、ディシジョンエイドにもそのまま反映されている。
このようなディシジョンエイドを活用しつつ、各治療選択肢(生物学的製剤や経口ステロイド維持療法など)のメリット・デメリットを提示し、患者さんの価値観や意向を尊重しながら、双方向的に話し合って患者さんの意思決定を支援することが重要である。講演者は、このディシジョンエイドを実際の診療でも患者さんに手渡し、一緒にページをめくりながら説明したり、持ち帰って家族と共有してもらったりしているという。患者さんからは「資料を読むことで自分の病気のことがよく理解できた」「家でじっくり考えることができた」といった声もあり、意思決定支援の実践に役立っているとのことであった。
まとめ
生物学的製剤は重症喘息において喘息増悪を抑制し、経口ステロイドの減量・中止を可能にする効果がある。これは重症喘息患者さんの予後改善に直結する大きなメリットである。しかし一方で、生物学的製剤は高額であり、その金銭的負担が導入の障壁となりうる。そして医療費に対する支払い許容度(コストに見合う価値の感じ方)は患者さん一人ひとりで大きく異なるため、画一的なアプローチは適さない。我々医療者は、生物学的製剤により「得られる効果」と「追加の金銭負担」を踏まえつつ、患者さん各々の価値観に基づいた医療を提供する必要がある。そのためのキーワードとなるのが「Shared Decision Making(SDM、共同意思決定)」である。SDMとは、最新で最良の科学的根拠(エビデンス)に基づき、患者と医療者が共に参加して治療方針を決定するプロセスを指し、重症喘息における生物学的製剤導入の意思決定において特に重要なアプローチの一つである(9)。SDMを実践するには、病状・治療効果はもちろん、患者さん個々の環境や価値観・嗜好も考慮に入れながら、医療者が考え得る選択肢それぞれのメリット・デメリット(費用面も含む)を丁寧に説明し、患者さんと「一緒に考えていく」姿勢が何より重要となる。
Take Home Message:
重症喘息患者さんのために医療従事者に求められているのは、「患者さんに生物学的製剤を無理に説得して飲ませること」ではなく、「患者さん自身が生物学的製剤治療を行うかどうかを決めるために必要な情報を提供し、意思決定できるよう支援すること」である(9)。患者さんが自ら納得し、選択した治療を受けることができるよう、我々医療者は伴走者としてサポートしていくことが大切である。
参考文献(References)
1. World Health Organization. Asthma [Internet]. 2021 [cited 2022 Apr].
2. 厚生労働省. 平成26年人口動態統計 [Vital Statistics of Japan 2014]. 厚生労働省; 2014.
6. Yamanaka H, Tanaka E, Nakajima A, et al. Changes of drug use and disease activity in rheumatoid arthritis patients over 2000–2018: results from a large observational cohort (IORRA study). Mod Rheumatol. 2020;30(3):814-830.
9. Tamada T, Kaneko Y, Kataoka M, et al. 重症喘息患者における生物学的製剤導入に至らなかった要因の検討 (KOFU study). Therapeutic Research. 2021;42(12):860-868.
11. 厚生労働省. 受診率向上施策ハンドブック ~明日から使えるナッジ理論~ [Internet]. 2019 [cited 2025 Mar].
参考書籍: 中島俊. 『入職1年目から現場で活かせる!こころが動く医療コミュニケーション読本』医学書院, 2023.
関連キーワード
#重症喘息 #喘息 #生物学的製剤 #共同意思決定 #意思決定支援 #高額療養費制度 #副作用 #ステロイド #ディシジョンエイド #ナッジ理論