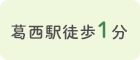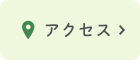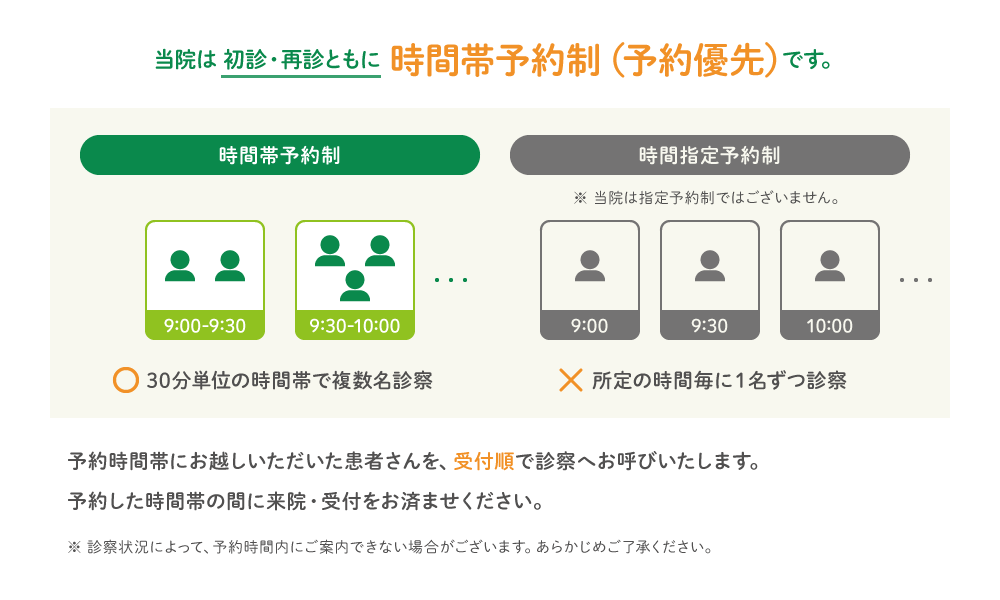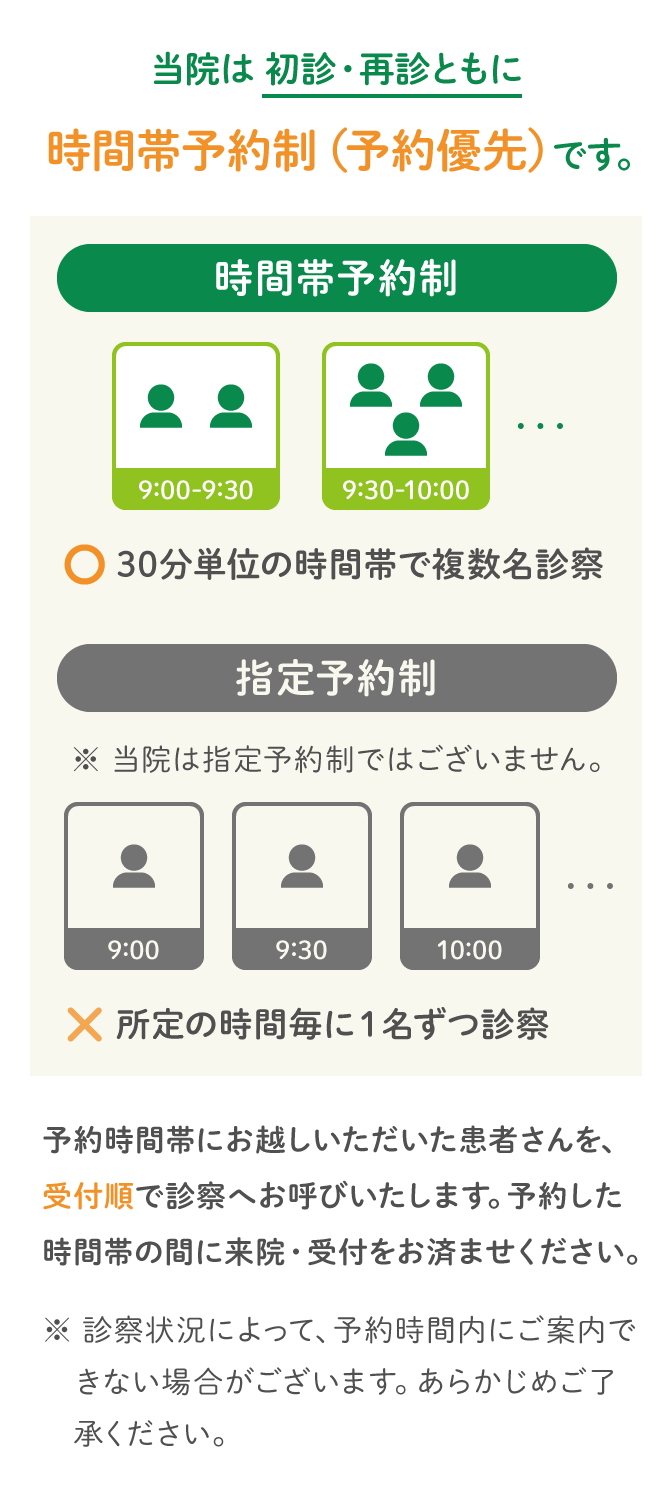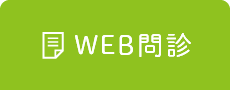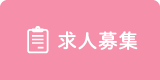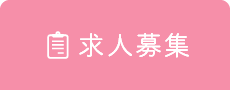内科について
 内科では、風邪や腹痛、発熱といった日常的な身体の不調や疾患から、高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病といった生活習慣病の治療まで、幅広い診療を行っています。
内科では、風邪や腹痛、発熱といった日常的な身体の不調や疾患から、高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病といった生活習慣病の治療まで、幅広い診療を行っています。
当院では、みなさんのかかりつけ医として地域の方々が気軽に相談することができる雰囲気づくり、丁寧な診療を行っています。
何かお困りのことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
風邪
 風邪(かぜ)は鼻やのどに微生物が感染して起こり、咳、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、声がれ、発熱などの症状があらわれます。原因のほとんど(80~90%)はウイルスです。その他の原因として細菌、マイコプラズマ、クラミジアなどもあります。風邪を起こすウイルスには数百種類以上もの種類が存在し、毎年のように新たな型のウイルスが出現します。このため成人で平均年に2~3回、小児ではそれ以上繰り返し風邪を引いてしまうと言われています。風邪ウイルスに対しては一部のウイルス(インフルエンザ)を除いて特効薬がなく、症状をやわらげる治療が主体となります。通常は1週間程度で自然治癒が期待出来ます。
風邪(かぜ)は鼻やのどに微生物が感染して起こり、咳、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、声がれ、発熱などの症状があらわれます。原因のほとんど(80~90%)はウイルスです。その他の原因として細菌、マイコプラズマ、クラミジアなどもあります。風邪を起こすウイルスには数百種類以上もの種類が存在し、毎年のように新たな型のウイルスが出現します。このため成人で平均年に2~3回、小児ではそれ以上繰り返し風邪を引いてしまうと言われています。風邪ウイルスに対しては一部のウイルス(インフルエンザ)を除いて特効薬がなく、症状をやわらげる治療が主体となります。通常は1週間程度で自然治癒が期待出来ます。
風邪の原因と検査
主な風邪の原因は下記のようになります。また、当院にて迅速検査に対応しているものをまとめます。風邪にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
| 原因 | 特徴 | 当院で検査可能 |
|---|---|---|
| インフルエンザウイルス | 発熱・関節痛・筋肉痛・頭痛などがあらわれます。治療薬としては、内服薬・吸入薬・点滴があります。 | 〇 |
| RSウイルス | 鼻水・咳などの気管支症状があらわれます。乳児に感染すると重症化することがあります。 | × |
| ライノウイルス | 風邪の原因として最も多いものです。春と秋に流行しやすいです。 | × |
| コロナウイルス | 風邪の原因としてライノウイルスの次に多くなっています。冬に流行しやすいです。 | 〇 |
| パラインフルエンザウイルス | パラインフルエンザウイルスを原因とした風邪症状があらわれます。 | × |
| アデノウイルス | プール熱やはやり目で知られるウイルスです。喉や目に症状があらわれやすく、夏に流行します。 | 〇 |
| コクサッキーウイルス | 手足口病やヘンパンギーナで知られるウイルスで夏に流行します。 | × |
| ヒトメタニューモウイルス | 乳児に感染すると重症化することがあります。症状はRSウイルスに似ています。3~6月に流行します。 | × |
抗生剤の適正使用
このように、原因の8~9割がウイルス感染である風邪に対し漫然と抗生剤を使用することは無効であるばかりでなく、耐性菌も引き起こすため避けなければいけません。一方で風邪によく似た症状で起こる、抗生剤の使用が必要な細菌感染も一部に存在します。
ウイルス感染と細菌感染を区別するために有用な検査として炎症反応検査(CRP)や、迅速診断検査法があります。CRP検査は通常ウイルス感染では上昇が見られず(例外的にアデノウイルスでは上昇が見られることがあります)、細菌感染などでは上昇を認める点で有用です。また迅速診断検査法では、一部感度の問題はありますが「インフルエンザ」「溶連菌」「アデノウイルス」「RSウイルス」「マイコプラズマ」などを5~15分程度で調べることが可能となっています。
当院では耐性菌予防の観点から基本的にかぜウイルス感染に対しては抗生剤を処方しておりません。ただし細菌感染が疑われる場合には、症状や経過に応じてCRPや迅速診断検査、レントゲン検査を行い細菌感染の可能性が高いと考えられた場合には抗生剤を処方しております。
| 原因 | 特徴 |
|---|---|
| 溶連菌 | 「のどかぜ」の症状を起こし、大人から子どもまで感染します。 適切に治療しないと繰り返し再発するため処方された抗生剤は最後まで飲み切るようにして下さい。 溶連菌迅速検査で診断します。 |
| 細菌性肺炎 | 原因菌として肺炎球菌、インフルエンザ桿菌、マイコプラズマなどがあります。 レントゲン検査で診断を行い、推定菌により治療薬を選択します。 |
| マイコプラズマ | 頑固な咳が特徴で、よく家族内感染を起こします。 診断には血液検査に加え、迅速検査もありますが、感度はあまりよくありません。 長引く風の原因となっていることがあります。 |
| 百日咳 | 百日続く咳と形容されるように、咳が長引くことが特徴です。 症状を悪化させないためには感染後なるべく早く治療することが重要です。 診断には血液検査を行います。 |
| 副鼻腔炎 | かぜ症状に引き続き発熱や頭痛、副鼻腔叩打痛(頬や眉間をたたく痛み)が起こります。 時期(急性と慢性)や原因(好中球性と好酸球性)により治療が異なります。 |
生活習慣病
高血圧
 血圧が常に正常の範囲を超えて高いのが高血圧の状態です。この状態が続くと、血管は常に強い圧力に晒されて、動脈硬化を起こし、それが脳血管障害や心不全など、重篤な疾患に繋がってしまいます。日本では、高血圧の患者様が多く、40~74歳までの男性では6割、女性では4割の方が高血圧の状態にあるとされています。降圧剤の内服と生活習慣の改善という両面から治療を行い、だんだんと降圧剤の服用を止め生活習慣によってコントロールしていくのが理想です。血圧は、病院の診察室で測定した場合、収縮期(上)が140mmHg以上、拡張期(下)が90mmHg以上であると高血圧とされます。しかし、早朝型高血圧の危険性がわかってきたことや、診察室では限られた時間にしか測定できないことなどから、近年では家庭で、時間を決めて毎日ご自身で測定する家庭血圧を重視するようになってきました。そのため40歳を超えたら、毎日血圧を測定する習慣をつけて、血圧をコントロールすることをおすすめします。
血圧が常に正常の範囲を超えて高いのが高血圧の状態です。この状態が続くと、血管は常に強い圧力に晒されて、動脈硬化を起こし、それが脳血管障害や心不全など、重篤な疾患に繋がってしまいます。日本では、高血圧の患者様が多く、40~74歳までの男性では6割、女性では4割の方が高血圧の状態にあるとされています。降圧剤の内服と生活習慣の改善という両面から治療を行い、だんだんと降圧剤の服用を止め生活習慣によってコントロールしていくのが理想です。血圧は、病院の診察室で測定した場合、収縮期(上)が140mmHg以上、拡張期(下)が90mmHg以上であると高血圧とされます。しかし、早朝型高血圧の危険性がわかってきたことや、診察室では限られた時間にしか測定できないことなどから、近年では家庭で、時間を決めて毎日ご自身で測定する家庭血圧を重視するようになってきました。そのため40歳を超えたら、毎日血圧を測定する習慣をつけて、血圧をコントロールすることをおすすめします。
糖尿病
 糖尿病は、インスリンというホルモンが不足するか、うまく働かなくなって、エネルギーの源となるブドウ糖を分解できなくなり、血液中のブドウ糖が多くなってしまう疾患です。ブドウ糖が多くなることで血管が狭く、詰まったりするようになります。腎臓や網膜、神経などに合併症を引き起こすこともあるため、適切な治療が必要になります。
糖尿病は、インスリンというホルモンが不足するか、うまく働かなくなって、エネルギーの源となるブドウ糖を分解できなくなり、血液中のブドウ糖が多くなってしまう疾患です。ブドウ糖が多くなることで血管が狭く、詰まったりするようになります。腎臓や網膜、神経などに合併症を引き起こすこともあるため、適切な治療が必要になります。
なお、糖尿病は1型と2型に分類され、1型はインスリンの産生不良、2型はインスリンの活動不良が原因となり、日本では95%が2型の糖尿病となります。2型の糖尿病は、中高年に多く、大きく生活習慣と関わっています。診断は血液検査や尿検査などで行います。近年では、当日の食事の影響を受けない血液中の酸化ヘモグロビン(ヘモグロビンA1c)の数値を重要視します。糖尿病自体は、完治することができませんが、2型の糖尿病は生活習慣の改善を中心に、血糖値を下げることによってコントロールし、合併症を起こさないようにすることが大切です。
脂質異常症(高脂血症)
 健康診断の血液検査などで、中性脂肪やコレステロールといった用語を聞くことがあると思います。これが血中の脂質をあらわす指標で、血中に脂質が多すぎると、血管に負担がかかるとともに、血管内部に脂質が溜まって、動脈硬化を起こし、脳血管障害や心不全などにつながる可能性もあり、注意が必要です。
健康診断の血液検査などで、中性脂肪やコレステロールといった用語を聞くことがあると思います。これが血中の脂質をあらわす指標で、血中に脂質が多すぎると、血管に負担がかかるとともに、血管内部に脂質が溜まって、動脈硬化を起こし、脳血管障害や心不全などにつながる可能性もあり、注意が必要です。
特に、肥満との関係が高いため、適正体重にすることを目標に、食事や運動などで生活習慣をコントロールしていくことが大切です。食事や運動によるコントロールがうまくいかない患者様については、薬物療法をお勧めします。
高尿酸血症
 尿酸は、身体を動かしたりするために必要なプリン体という物質の燃えかすで、専門的には代謝物と言います。プリン体の多くは肝臓で分解され、尿酸となって最終的には尿や便に含まれて排泄されて行く仕組みになっています。しかし、何らかの理由で、尿酸が作られすぎたり、うまく排出できなかったりすると、血液中に尿酸が含まれる量がどんどん増えていってしまいます。この状態が高尿酸血症です。はじめは自覚症状がなく、ある時点で尿酸が飽和すると、結晶化して関節などの中に蓄積するようになり、ある日突然激しい痛みとなってあらわれます。この状態になると痛風という疾患になります。
尿酸は、身体を動かしたりするために必要なプリン体という物質の燃えかすで、専門的には代謝物と言います。プリン体の多くは肝臓で分解され、尿酸となって最終的には尿や便に含まれて排泄されて行く仕組みになっています。しかし、何らかの理由で、尿酸が作られすぎたり、うまく排出できなかったりすると、血液中に尿酸が含まれる量がどんどん増えていってしまいます。この状態が高尿酸血症です。はじめは自覚症状がなく、ある時点で尿酸が飽和すると、結晶化して関節などの中に蓄積するようになり、ある日突然激しい痛みとなってあらわれます。この状態になると痛風という疾患になります。
痛風は進行すると、全身に拡がり、様々な関節に障害を起こし、尿路結石や腎障害などを併発する傾向にあります。さらに痛風をもっている人は脳血管障害や心筋梗塞なども合併しやすくなると言われており、尿酸値が高い方は尿酸値を下げていくことが大切です。
治療は薬物治療を中心に、プリン体の多い食事や飲酒などを控える生活習慣の改善が必要になります。なお、運動はプリン体を代謝して尿酸が増える原因となりますので、軽度なものに止め、激しい無酸素運動などは控えめにする必要があります。
骨粗しょう症
 骨粗しょう症は、骨を構成する組織の量が減少してしまったり、組織の質が劣化してしまったりして、骨格を構成する骨がもろくなってしまう疾患です。
骨粗しょう症は、骨を構成する組織の量が減少してしまったり、組織の質が劣化してしまったりして、骨格を構成する骨がもろくなってしまう疾患です。
以前は高齢者に多かったのですが、近年では、無理なダイエットなどが原因となって、若い女性などの発症も目立つようになってきました。食生活などで身に覚えのある方は、一度専門医の診断を受けてみることをお勧めします。
当院では2型糖尿病や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、またぜんそくでステロイドの治療を行っている方に骨密度検査をお勧めしております。精密検査(DEXA)をご希望される場合は連携施設にて検査を受けて頂くことができます。治療は活性型ビタミンD製剤やビスフォスフォネート製剤などで行いますが、運動療法や栄養療法と組み合わせて頂くとより効果的です。
不眠症
 睡眠は肉体的、精神的に休息を得るために大切なものです。しかし、ストレスなど、様々な外的要因に左右される現代では、睡眠自体をしっかりととることが難しい状況もあります。眠いのに眠れない、眠りが浅くてしっかりと寝た気がしない、寝てもすぐに目覚めてしまう、予定以上に朝早く目覚めてしまうといった、いわゆる不眠症の症状を訴える方が増えています。
睡眠は肉体的、精神的に休息を得るために大切なものです。しかし、ストレスなど、様々な外的要因に左右される現代では、睡眠自体をしっかりととることが難しい状況もあります。眠いのに眠れない、眠りが浅くてしっかりと寝た気がしない、寝てもすぐに目覚めてしまう、予定以上に朝早く目覚めてしまうといった、いわゆる不眠症の症状を訴える方が増えています。
睡眠による休養がしっかりととれないことから、肉体的な不調を来すだけではなく、精神的にも様々な不調を来します。
当院では、「オレキシン受容体拮抗薬」や「メラトニン受容体作動薬」など、なるべく依存性・耐性を起こしにくい薬を中心に治療を行い、長期的には睡眠薬を減薬・中止できることを目指します。
逆流性食道炎
 食道から胃への食物の流れは、食道の蠕動運動と胃の入り口にある逆流を防ぐための弁である噴門の働きによって、口からの流れをしっかりと保っています。しかし、何らかの影響で、食道の蠕動運動や胃の噴門の活動が弱まって締まった場合、胃へと流れていった食物や、胃液などが食道へと逆流する現象が起こります。胃の内部は強酸性の胃液に耐えるための仕組みをもっています。ところが、一度胃に入ったものが、食道へ逆流すると、食道は強酸性の胃液に耐える仕組みを持っておらず、炎症を起こしてしまいます。これが逆流性食道炎です。治療としては、胃酸の働きを抑制する内服薬の服用を中心とした、薬物療法を行います。
食道から胃への食物の流れは、食道の蠕動運動と胃の入り口にある逆流を防ぐための弁である噴門の働きによって、口からの流れをしっかりと保っています。しかし、何らかの影響で、食道の蠕動運動や胃の噴門の活動が弱まって締まった場合、胃へと流れていった食物や、胃液などが食道へと逆流する現象が起こります。胃の内部は強酸性の胃液に耐えるための仕組みをもっています。ところが、一度胃に入ったものが、食道へ逆流すると、食道は強酸性の胃液に耐える仕組みを持っておらず、炎症を起こしてしまいます。これが逆流性食道炎です。治療としては、胃酸の働きを抑制する内服薬の服用を中心とした、薬物療法を行います。